食中毒疫学とは何か、どんな役に立つのか
「食中毒疫学とは何か」という質問に適切に答えられる人はあまりいないだろう。これが筆者の偏見ならばよいのだが、現実にはどうもそうではないらしい。端的に言うと、食中毒疫学というのは、「食中毒の発生状況を調べて、それを予防に役立てるための学問」であると言えるが、現状ではこの答えの前半部分だけが一人歩きしているようだ。食中毒の発生状況を調べると言っても、これには二つの面がある。一つは、全国的、あるいは一部の地方で発生している食中毒を調べて、統計的に分析することであるが、もう一つは、現在集団発生している食中毒を調べて、その原因を早く同定して、食中毒が蔓延しないようにすることが目的である。何れにせよ、食中毒疫学の最大な(唯一の、と言っても過言でない)目的は、食中毒の発生を可能な限り予防することにある。この目的を忘れた疫学調査は完全に無意味であることを忘れている人たちが多いのは、残念なことである。
そこで、一つの面、すなわち食中毒統計について考えてみよう。今の日本の食中毒統計は、いわゆる「受動的報告による統計」である。しかし、受動的統計では食中毒のわずか一部が捕捉されるのみで、真の食中毒発生状況は分からない。CDC(下記参照)から、次のような図が発表されているが、受動的報告が実際の食中毒疾病発生数に比べると、数百分の1程度であるのは、常識であるとさえ言える。したがって、受動的報告にのみ依存している統計にはあまり意味がない。積極的調査によって実態をつかみ、これを将来の食中毒発生予防に役立てること、またリスクアセスメントに役立てて、どのような疾病を予防することの優先順位が高いか、そのような予防にどれだけの資金をつぎ込むべきかという、方針決定に役立てることが究極目的である。
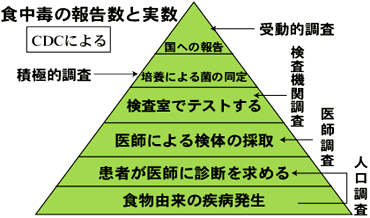
次に、上に上げた目的の二つ目の現在発生中の食中毒事件の捜査について考えてみよう。この捜査で最も重要な目的は、食中毒の蔓延をなるべく早く防ぐことである。原因因子が分からなくても、原因食が想定できれば、それを市場から引き上げることによって食中毒の蔓延をとめることが可能になる。雪印の脱脂粉乳に由来する黄色ブドウ球菌毒素中毒事件は、この考え方が有効に使われれば、被害者の数は多分、発生数の10分の1か、それ以下で済んだであろう。このようなすばやい予防策をとるためには、コホート・スタディ、あるいはケース・コントロールスタディという方法が必要である。これを詳細に説明する紙面はないが、簡単に言えば、患者が何を食べたかだけでなく、健常者が何を食べたかをも調べることによって、確率的にどの食物が、限りなく黒に近いかを確率として算出することができ、原因因子の同定にはるかに先立って原因食が推定できる方法である。残念ながら、日本ではこの方法が一般的に行われているとは言いがたい。アメリカのハンバーガー・チェーンで発生した大腸菌O157:H7による集団中毒事件でも、レストランの営業停止に踏み切ったのはO157が同定されるより前であって、USDA(米国農務省)の係官は、「原因因子が見つかる前に確率だけでレストランの閉鎖に持っていくのは乱暴ではないか」という質問に対して、「これが国民の命に関わるような被害を食い止める唯一の方法である」という答えを与えている。
前出の米国疾病管理予防センター(CDC; Centers for Disease Control and Prevention)から病気と死亡の週間報告(MMWR)という出版物が出されている。あらゆる疾病や事故についての報告や統計がその内容の中心である。ここから毎年出される食物由来の疾病発生事件報告のまとめが11月10日付で筆者の手許に送られてきたが、その内容に、中々興味のあるものがある。「食中毒の集団発生の調査の目標は、食中毒の予防と、企業の予防対策を促進することにある。このために公衆衛生係官は農場から食卓にいたる食品取り扱い過程で、必須管理点を見つけ、それをコントロールするのである」というコメントもその一つである。事故が起きた後で、食品提供業者の営業停止をしたところで、問題の解決には役立たない。公衆衛生係官には、どんな加工過程で、何が起きて、それをどうやったら、食中毒発生が抑えられるのかを明確にし、予防対策を迅速に講ずることが求められるのである。これには、科学的な判断ができる能力を係官も企業も学ばなければならない。日本の規制が科学的に決められていないことは、既に既知の事実であると言っても良い。中央政府から科学的根拠に基づく仕事をしないでは、末端でそれができるはずはない。
|
■2006年10月16日 前提条件プログラム IV 日々のサニテーション作業の記録 (National Seafood HACCP Allianceの「魚介類製品の製造におけるサニテーション・コントロールの手順」から (1) 3.清浄化と衛生化(クリーニングとサニテーション) クリーニングとサニテーションは前提条件プログラムの中で、最も重要であり、明らかなものであろう。アメリカの、National Seafood HACCP Alliance for Training and Education(魚介類のHACCP連盟)では、 ☆Sanitation Control Procedures for Processing Fish and Fishery Products, First Edition, 2000(魚介類製品に関するサニテーション・コントロール手順)を出版しているので、これを参考にすると良い。 (http://seafood.ucdavis.edu/sanitation/scpmanual.htm参照) HACCP連盟のサニテーション・コントロール手順は、普遍的な手順を述べているものの、細部にわたっているので、本著ですべてを紹介するわけには行かないので、この概略を述べるにとどめておく。特に、「サニテーション・コントロール・ガイドの例」では、食品接触面の清浄化、衛生化について簡潔に述べられているので、これを下に示す。 表3-1 サニテーション・コントロール・ガイド
(注2)ATPを測定する蛍光装置 (注3)菌数計測、あるいはATP測定が過大であれば、清浄化、衛生化の方法を考慮しなおす。 (注4)5段階法:(1)乾燥状態での清掃、(2)水ですすぐ、(3)洗剤で洗浄する、(4)水ですすぐ、(5)消毒剤(衛生化剤)に浸す(アメリカの場合は、衛生化剤を適切な濃度で用い、その後空気乾燥して、仕事に入る。日本では消毒剤使用後に水すすぎが必要)。 (注5)消毒剤の濃度の規定(アメリカの場合):21 CFR 178.1010参照。 *すすがないで用いられる最大値
以上にも明らかなように、手順を決めて、それを文書化しておくことが必要である。この文書化した手順をSOPと言い、それが清浄化、衛生化に関したものの場合にSSOP(Sanitation Standard Operating Procedures)という。FDA監督下に義務化されている魚介類のHACCP規制では、SSOPは作っておくべきであるとしているが、衛生化状態のモニタリング、非衛生状態の是正、清浄化、衛生化のコントロールの記録を付け、保管することは、この規制下で義務化されている。FDAでは、サニテーション状況のキー・ポイントとして、次の8項目を挙げている。(1)食品および食品接触面と接触する水、あるいは氷を作る水の安全性、(2)器具、手袋、作業衣を含む食品接触面の状況と清潔さ、(3)食品、包装材、器具、手袋、外衣その他の食品接触面が不潔なものと交差汚染を起こさないようにすること、生の食品と、加熱調理した食品の接触を防止すること、(4)手洗い装置、手の消毒装置、およびトイレット設備の保全、(5)食品、包装材、食品接触面の、潤滑剤、燃料、ペスティサイド(殺虫・殺鼠剤)、洗浄剤、消毒剤、凝縮水、その他の化学的、物理的あるいは生物的な汚染物質による汚染(偽和化)からの保護、(6)毒性のある化学品の適切な表示、保管、使用、(7)食品、食品包装材、食品接触面を微生物で汚染する恐れのある従業員の健康状態のコントロール、(8)食品工場からペストの排除。(21 CFR Part 123.11参照) 何れにせよ、GMPと、サニテーションがしっかり実施されていて、その基礎の上にHACCPが導入できるのであって、GMPの部分である、従業員や経営者の教育・訓練、従業員の衛生行為、従業員の衛生状態のチェックと、健康でない(病原微生物による食品汚染を起こす恐れのあるような状態:例えば、食物由来の疾病にかかっている)従業員を排除することができるように、普段からの教育、訓練が行き届いていること、などが確立されていなければ、HACCPを導入することは不可能である。ただし、これは、GMPあるいは前提条件プログラムが完璧でないと、HACCPが出来ないといっているのではない。前提条件プログラムによって、HACCPでコントロールし難いハザードが適切にコントロールされていることが大切なのであって、これらのハザードが完全無欠にコントロールされていなければならないということではない。 前提条件プログラムにも、記録が必要である。このことは、日々のサニテーション・コントロール記録として、あらかじめ決めておいた記録用紙に記録するのが簡単であろう。上記の、Sanitation Control Procedures for Processing Fish and Fishery Productsにも、この書式の例が示されている。以下にそれを記す。 ここに挙げた例は、一例として示しただけであり、個々の工場、作業、場所について、別々に作られるべきものである。例えば、男性のロッカー・ルームについてのサニテーション・コントロール記録、化学品保管についての記録、ペスト・コントロールについての記録、スライサーについての記録、など、個々の作業場所について、一度、このような書式を作っておけば、作業が単純化され、ミスも少なくなる。また、一つ一つの作業について、SOPが明確に作られ、従業員が容易に参照できるようにしておくことが必要である。記録をつけた場合、つけた人の署名と日時が記録されていなければならない。 Sanitation Control Procedures for Processing Fish and Fishery Productsには、サニテーションに関する8項目の詳細な説明が示されている。是非、一読をお勧めする。 ■2006年9月15日 前提条件プログラム III GMP以外のプログラム(2) (c) アレルゲン・コントロール:アレルゲンのコントロールには、数多くの要素があり、これらをすべてHACCPでコントロールするのは困難である。例えば、これらのコントロールの許容限界をどこに設定し、どうやってモニタリングするのだろうか?意図しないで起きるアレルゲンの混入は、ほとんどの場合、前提条件プログラムの一部でコントロールが可能であろう。例えば、サプライヤー保証、アレルゲンの入った原料と、そうでない原料の交差接触の防止は、保管場所を分別したり、製品製造の順序を考慮したり、クリーニング、サニテーションを徹底したり、従業員のアレルゲン・コントロールについての訓練などを徹底させたりすることによって、可能になるであろう。これらはすべて、HACCPプログラムで行われるのではなく、前提条件プログラムの範疇に入る。なぜならば、これらは、製造過程のステップのコントロールではなく、一般的な工場全体にわたるコントロールが効果的であるためである。アレルゲンの正しい表示をすることは、もちろん必要であり、これがラベルに印刷されていることを、ラベルのロットごとにチェックすることを、必須管理点とするか、PPで十分とするかは、各工場のコントロールがどのように出来ているかによる。 (d) 環境衛生プログラム:リステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)、あるいは環境由来のサルモネラや黄色ブドウ球菌などのコントロールは、その由来が環境に基づくものであるため、さらにリステリア属の菌の検出などを行うことが必要であるため、HACCPで行うのは困難である。リステリアが問題を起こすことが多かった食肉加工業では、数年前から「環境衛生プログラム」を実施して、工場、特に食品接触面の衛生化を進めてきた。工場内の環境の微生物汚染を区域に分けて、汚染が起きやすいところ、食品接触面、特に加熱後の食品接触面あるいはそれに近いところを最重点として、操業中の汚染状態を検査する。リステリア・モノサイトゲネスがターゲットである場合には、リステリア属について、操業中に拭き取り、リステリア属の検出・モニタリングを行い、汚染があった場合にはプロセスの川下から川上へと拭き取りの場所をいろいろしらべて、汚染が強くなってきて、突然なくなったとすると、この境目にあるのが、汚染源である可能性が高い。このようにして、汚染の発生源を発見し、これを徹底的に清浄化、衛生化することによって、汚染源を取り除くというような方法を講ずる。 前提条件プログラムとHACCPの関係について、いろいろな質問が寄せられる。これに関しては、 ☆ William Sperberらの、Dairy, Food and Environmental Sanitationに掲載された論文(Roles of Prerequisite Programs in the Management of HACCP System, Dairy, Food and Environmental Sanitarians, Vol.18, No. 7、PP.418-423, 1998)が参考になる。 端的に言えば、「前提条件プログラム(Prerequisite Programs)とは、HACCPの導入が容易なように、工場(その他の食品取扱所)の条件を整えるプログラムである」ということが出来るが、もう少し突っ込んで見ると、次のように言える:「HACCPでコントロールしにくい、あるいはコントロールする必要がないハザードを適切にコントロールするためのプログラム」が前提条件プログラムである。「前提条件」という言葉は、このプログラムが完璧でなければHACCPが出来ないというような誤解を受けやすい。前提条件プログラムを完璧に行うのは、不可能であると言っても過言ではない。「出来るだけやる」という姿勢が必要であろう。実は、前提条件プログラムとHACCPは、相当程度に、「持ちつ、持たれつ」の関係にあり、お互いにそのシステムが得意とする、食品安全のハザードのコントロールを、それぞれ行って、総合結果として安全な食品が出来るのである。ただし、前提条件プログラムには、安全性以外の項目が入っていても差し支えない。ここでは、HACCPを考える上で、安全性に的を絞って考えることにする。もちろん、「不潔な工場からは清潔な製品は生まれない」のであって、適切な前提条件プログラムの実施がまさに前提条件となることは当然である。 相互依存(持ちつ持たれつ)の関係というのは、例えば、環境由来のハザードは、それがプロセスおよび製品にスペシフィックな(特定される)ものでないため、プロセスのコントロールに主眼を置いたHACCPではコントロールがやり難いので、前提条件プログラムでコントロールする方が合理的なのである。 環境由来の汚染には人による汚染も含まれるであろう。日本では、よく、「髪の毛は経済的にも非常に大きなハザードなので、HACCPで取り扱うべきである」といわれるが、プロセスのどの段階で、「髪の毛の混入を許容限界以内に収まるように、リアルタイムでモニタリングし、是正措置をとる」ことが可能であろうか?髪の毛はやはり、粘着ローラーでの除去と、髪の毛をヘアネットなどで適切に覆うことによってコントロールするのが最も効果的であることは常識であろう。「髪の毛の混入防止をHACCPでやる」のであれば、どの点がCCPになり、何がCritical Limitになり、モニタリングはどうするのか、是正措置はどうするか、再発防止はどうするか、などを明らかにしてから議論すべきであろう。世界の常識にあえて異を唱えるのであれば、その科学的根拠を明らかにする義務がある。科学的根拠なしに自分勝手に適当な議論をする風潮がなくならないと、世界的に通用する安全性のコントロール手段の実施は不可能であり、日本の食品安全の将来は保証できない。 ■2006年9月8日 アメリカでの引越し 今日のブログは個人的な話で、皆様のお邪魔をしたい。興味のない方々は、無視して下さい。 アメリカへ帰ってきてから5ヶ月が経った。日本から送った、家具など一切無しではあるが、52箱になる荷物と一緒に過ごしたアパート生活に別れを告げて、他人に貸していた72 Paxwood Road, Delmar, NYの自宅が空いたので、引越しをすることになった。借家人が出たのが7月末。直ちに5年近く人に貸していた我が家を視察したが、やはり、いろいろな問題が出てきた。まず、家具をそろえなければならなかったこと、それに、カーペットが古くなっていて、家内の希望通りに、ハード・ウッド・フロアにしたかったこと、壁が内外とも汚れていたこと、地下室の湿気が多く、黴臭かったので、この防水工事と、壁の塗り直しが必要なこと、カーテンも日本に行く前から替えたいと思っていたものが、どうにもならないほど古くなっていたこと、屋根が古くなって、変色していたこと、木が茂りすぎていて、暗すぎる感じがした事、などなど、快適に住むために、思い切って、人を雇って、手入れをすることにした。とは言っても、大きな業者に頼んでいたのでは資金が膨大に掛かり、リタイアした身には、一寸きつ過ぎる。幸いに、留守の間に自宅を人に貸すのを依頼していた不動産業者が、すばらしく面倒見の良い人で、彼女に完全に依存することに決め、知り合いの業者を紹介してもらった。ちなみに、彼女は我々の留守の間に、出来る限りよいテナント(借家人)を、良い価格で見つけるために努力したばかりでなく、家の管理すべてを引き受けてくれ、我々としては、親身な仕事をしてくれる、頼りになる女史であり、我々としても正規の管理料金のほかに、多額のボーナスを払ったほど、素晴らしい仕事をしてくれた人である。 とは言っても、これだけの仕事をするのは、やはり相当な資金が必要である。家具は、最低必要限にとどめて、シンプルで気に入ったものを購入するために、脚を棒にして歩き回った。結局、今までに、革張りのソファーと安楽椅子、ベッド2台、箪笥2つ、鏡台つきの箪笥一つ、フロアランプ、デスクランプ、ナイトテーブル2台を買い揃えたが、まだ事務用のデスクと椅子が足りない。木が茂りすぎの問題は、業者に来てもらってディスカスした挙句、大手術をすることにした。22本の木を切り(大きなものは15メートル以上、その他でも6、7メートル)、その代わりに、10本の新しい(2メートル足らずくらいの)ものを植えることにした。樹を切って見ると、全体が、ぐっと明るくなった。家のフロアはカーペットの下がハードウッドであったので、これをサンドペーパーで削って、フィニッシュをし直したところ、非常に綺麗なものが現れて、満足できるものであった。ペイントがなかなか大変。細かいところに気を使ってくれる業者は有難いのだが、手間がかかる。屋内のペイントも、まだ完全に終わったわけではない。屋外、車庫はこれからである。2台の車が楽に入る、リモコンつきのドアのあるガラージは、内部の塗装と、天井の断熱材を入れなおすので、これも、まだこれからである。今は屋根の葺き替え作業中である。こちらの屋根はシングル(shingle)と呼ばれる、アスファルトを固めたようなもので作られるのが普通だが、25年程度しかもたない。これも良い材質を使ってやってもらうことにした。その上、家内が、「スカイライトが欲しい」と言い出して、屋根に穴を開けて、ガラスの天窓をつけることにしたので、この作業も簡単ではなかった。多数ある窓につけるカーテン、ブラインドなども、注文しなければならないので、大変な手間と時間と費用がかかる。これもまだ完成していない。それでも、アパートの方は、52箱プラスの荷物を運び出して、借りていた家具も引き取ってもらって、大車輪で掃除をして、管理人に査察をしてもらった結果、素晴らしく綺麗になっているという評価を得て、無事チェックアウトが出来たので、9月1日には漸く、自宅一軒だけを管理すれば良い状態に漕ぎ着けた。これから約2週間で、業者の仕事もすべて完了するであろう。家の手入れの費用はトータルで約500万円余りになるだろうか。痛い出費だが、必要な経費が殆どである。そうして、漸く、小さいながらも住み心地の良い我が家になる。小さいとは言っても、建坪約50坪、土地は約400坪である。平屋(Ranch style house)で、地下室が殆ど家全体の下にあるので、2人には十分である。間取りはベッドルーム2つ、スタディ、フル・バスルーム2つ、それに台所と、ダイニング・エリア、さらに、サン・ルームといって、ガラス張りの、冷暖房はないが、一年のうち半分は楽しめる部屋がある。この部屋で朝食をとるのは、夏の間の楽しみである。22本の樹を切らせたが、隣の家との境界線には30メートル余りの松の巨木が3本、ノルウェーかえでの巨木が、前庭にそびえ、まだまだ10本余りの大樹が茂っている。5年前に植えた松の木が4メートルくらいに育っていたので、この管理も手間がかかる。ただし、こちらでは、日本のように、松の木に人が登って、緑をつむようなことはしない。延び過ぎた枝を切り落とすくらいが手入れの内容である。落葉樹が数本あって、秋の終わりには落ち葉掻きで相当な仕事がある。もう、秋風が吹いていて、芝の伸びも、それほどではないが、春から夏にかけては、毎週、1時間余りの芝刈りの仕事が待っていることになる。もちろん、ガソリン・モーターで動く芝刈り機は各家庭で不可欠なものである。落ち葉焚きは、空気の汚染を起こすので禁止されている。落ち葉は、リサイクル可能な、町の条例で決められた規格の紙袋に入れて、町の係員が持って行ってくれるのであるが、秋の落葉シーズンの間の数週間は、道端に山積みにしておくと、バキューム・トラックが通って、吸い取って行ってくれる。落ち葉は、堆肥にするということである。出来た堆肥は、家庭菜園で花や野菜を作る人たちが喜んで買って行くらしい。木の枝などを切った場合も、1.3メートルくらいに切って道端に置いておくと、市の係員が取っていく。 家を人に貸すのは、経済的には絶対に必要ではあるが、借家人は、庭などの手入れはもちろん、やってくれないので(芝を刈るのは義務であるが)、これから、芝の種を蒔いたり、そのために土を多少入れたり、という仕事が待っている。しかし、これも楽しみの一つである。来年は、家の周りを花で飾ろうと、今から考えている。近隣の家々は、殆どが綺麗に飾っている。塀が全く無いので(禁止されている)、芝生と花と、大きな樹に覆われた街全体が、非常に和やかな雰囲気になっている。アメリカの町ではゾーニングがはっきりしていて、住宅地は個人の家だけ、商店はもとより、アパートも通常の住宅地には建てることが出来ない。ゾーニングの変更は、町のゾーニング委員会で許可された場合のみ許されるが、この許可は十分な条件を満たした場合のみに許される。通常の場合、住宅地のほかの用途への転用は全く認められない。従って、隣に高いビルが建って、日当たりが悪くなったなどということは起こり得ない。ちなみにデルマーでは、住宅は2階以内である。人口は2000年で8,700人、デルマー(村にあたるだろうか)も含めた行政単位であるベツレヘム町は31,300人である。ベツレヘム町はアルバニー郡に属するが、郡の人口は約30万である。ニューヨーク州の人口は1900万、最大の都市はもちろんニューヨーク市で、人口800万である。ニューヨーク州の州都がニューヨーク市ではないことを知っている人は比較的少ない。州都はアルバニーであり、州議会の建物は、ヨーロッパ風の王宮のような威厳のあるものである。この州議事堂のすぐ隣には州庁舎があるが、これはまた打って変わった現代的な高層タワーと、4つの塔からなっている。夏は暑いときもあるが、通常は日中でも26℃位で、乾燥しているので過ごしやすい。記録では42℃というのがあるが。北緯45度、大西洋の影響があるためいくらか大陸性の気候の厳しさは和らぐが、それでも零下20℃くらいまで下がることがある。家の中が暖かいため、それほど厳しくは感じない。場所によっては山が見えて、全体に緑が多く、快適なところであり、我々はここが非常に気に入っている。ニューヨーク市の真ん中まで、車で約2時間半、電車でも2時間余り、240キロ程度で、近からず、遠からずと言える。 ■2006年7月31日 前提条件プログラム II GMP以外のプログラム (1) 前提条件プログラムのその他の要素:前提条件プログラムには、上記のアメリカのcGMP規制に規定されたもの以外にも、いろいろな要素がある。cGMPに簡単に触れられているものもあるが、サプライヤー保証の確立、リコールシステムとトレーサビリティの確保、アレルゲンのコントロール、環境衛生プログラムなどがそれである。後で述べるように、HACCPでコントロールが容易にできる危害要因と、コントロールしにくい危害要因があることを認識しておかなければならない。 (a) サプライヤー保証:原料、包装材、薬剤などのサプライヤー(供給者)に、品質、安全性などを保証させることであり、マクドナルドなど、アメリカ大手のプログラムで、有名になった。サプライヤーが原料の製造などにHACCPを導入していることをサプライヤーの認証の条件にしたり、原料などの仕様を決めて、それを守ることを契約の条件にしたり(遵守証明;COC)、あるいは成分について、一定の分析値を守らせたり(分析証明;COA)することで、品質、あるいは安全性を確保しようというプログラムがある。サプライヤー保証プログラムでは、サプライヤーとバイヤーが協議して、仕様を決め、それを両者で遵守していくことが中心になる。サプライヤー保証と言っても、サプライヤーに一方的に保証させることがすべてではない。望ましい安全性を確保できるように科学的に正しい仕様を決めるのであるが、無理な仕様の押し付け、力関係のみで決まる厳しすぎる仕様、逆に緩すぎる仕様は対費用効果が低いことになり、健全なサプライヤーの育成につながらないので、避けるべきである。遵守できなかった場合の製品の処置、罰則なども、あらかじめ決めておく必要がある。
(b) リコールシステム:食品会社が、市場に出した製品に、安全性の問題、品質の問題、あるいはラベルに誤りのあった場合などには、市場に出ている製品を回収し、問題のある製品が消費者の手に渡らないようにして、問題を是正するか、あるいは製品を廃棄する必要がある。このような製品の回収、あるいは製品の流通の停止をリコールという。リコールは、健康上、安全上の懸念によって政府から命令されることもあるが、会社が自主的に行って、会社に対する世間の評価を損なわないようにする場合も多い。リコール作業が迅速に、完全に行われることが、リコールのコストを削減し、会社の評価に関する損失、あるいは健康上の被害などによる消費者、流通業者に対する損害賠償も含めて、会社への損害を最小限に止める鍵になる。リコールを効果的に行うためには、そのためのシステムが必要である。システムの要素としては、次のようなものがある。 ■2006年7月24日 前提条件プログラム I カナダのFSEPおよびアメリカのGMP 1.前提条件プログラムの発祥 1991年のカナダ政府によるFSEP(食品安全推進プログラム)が提唱した「前提条件プログラム」(Prerequisite Programs)がHACCPの導入に及ぼす重要性は、今では、疑う者はいないであろう。第1章HACCPの概要 に述べたように、この考えは、アメリカのcGMP規制を更に発展させたものであると考えてよい。 ただ、発祥の経路から見ると、カナダでGMPと言う場合には、アメリカのcGMPよりも相当に広い分野にわたる、PPすべてを含んだものと考えるのが妥当である。以下、前提条件プログラムについて、説明しよう。「前提条件」と言う言葉は、誤解を招きやすい。これらのプログラムの要素、すべてを完璧に実施しなければ、HACCPができないという意味ではない。前提条件プログラムでコントロールするハザードと、HACCPでコントロールするハザードは、種類が異なるといっても良いであろう。前者は、工場全体にわたるプログラムであって、これでコントロールしようというハザードは、特定の製品、特定のプロセルのステップでのコントロールは行いにくい、あるいは行ったとしても効果的でないものである。また、前提条件プログラムで行う仕事は、工場全体にわたるだけでなく、非常に種類と数の多いものであり、これらをすべて、完璧にコントロールしようとすれば、仕事が複雑になり、過重になりすぎるのである。この中で特にコントロールが必要なものを、ISO22000ではオペレーションPRPと言っている。しかしながら、前提条件プログラムをPRPと、オペレーションPRPとに明確に分けられるものではない。製品の種類、性質によって、ある仕事がどうしても必要な場合と、同じ仕事でも実施要求が緩やかな場合とがあるのは当然である。前提条件プログラムを一応、完成させて、それに基づいてハザード・アナリシスを行い、HACCPでのコントロールが難しいか、複雑になりすぎるかするハザードが適切にコントロールされていることが確かめられれば、前提条件プログラムの使命の主要な部分は達成されたことになり、それに基づいて、HACCP計画を立てることができる。さらに、前提条件プログラムには、安全性の確立以外の目的が入っていても構わない。これに比して、HACCPでは、安全性のみを取り扱う。 2.前提条件プログラムとは 現在のPPには非常に広範囲の項目が含まれている。それらをあまり複雑にならない程度に、以下にあげてみよう。 GMP: まず、アメリカのcGMP(現行適正製造基準と訳す)(CFR タイトル21、パート110)に含まれているものから見てみよう。この規制文では、主に、目的達成のために、どのようなことをすべきかについて、概要を規定している。細かい規定はなく、細部は地方自治体、あるいは企業の判断に任せてあり、目的を達成するためにはいろいろな方法があることを認め、新しい方法の発明・工夫・導入を奨励しているのが特徴である。以下にアメリカのcGMPに挙げられている項目を簡単に説明する。 (a) 従業員:ここには疾病の管理(食品接触面、あるいは食品そのもの、包装材などに汚染を起こす危険性が通常に考えて起きやすい状況がある従業員の排除など)、従業員の清潔さと衛生行為の遵守(手洗い、服装、装身具の排除、ヘアネット、身につける化学品や飲食の制限など)、従業員の教育訓練、監督者を明らかに指定することが必要とされている。 (b) 工場と敷地:ここでは、工場を設置する環境条件(製品に汚染が起きないようにするため)、工場にほこりや泥が入らないようにするための道路、駐車場の舗装、廃棄物処理のシステム、建築とデザイン(食品製造の目的を保つことが出来、その目的達成を推進することが適切に出来るもの:衛生的デザインの概念が必要。この考え方が日本では弱いように感じられる)、設備の設置、汚染が起きないような構造、清浄化・衛生化がしやすい構造、空気の流れや気圧・換気、ペスト(有害動物)の進入防止などがここに規定されている。 (c) 清浄化・衛生化:衛生状態を保全して汚染が起きないようにすること、有毒物質{洗浄剤・消毒剤、機械の運転に必要な化学品(潤滑油など)、ペスト・コントロール薬剤、検査に必要な化学品なども含まれる}の表示・保管(別途規制がある)・使用法、ペスト・コントロールについては、これを排除し、侵入を防止する建物の構造が要求されていると同時に、排除に効果的な方法を採用することが決められている。さらにこの項目では、衣服、手、食品接触面、非接触面を含めた清浄化、衛生化を行い、食品および包装が汚染されないようにすることが要求されている。 (d) 衛生施設と管理:水の供給として、安全で適切な衛生状態の水が、適切な温度と水圧で供給されることが規定されており、配管は、水の逆流を防ぐ構造であり、交差配管(汚水と清浄水が混ざるような配管)がないことが必要であるとされる。たとえば、洗浄用のホースの口が床に触れたり、逆流したりしないようになっていることが必要である。さらに、下水の処理が適正に行われること、トイレット設備が衛生的な状態に保たれ、常に正常に働くように保全されていること、トイレットのドアが、手で触れずに開閉できること、および、露出した食品のある部屋に向かって直接開閉しないこと。手洗い設備が整備され、洗剤、消毒剤が適切に備えられ、衛生的なタオル(紙タオルなど、使い捨てタオル)または手の乾燥装置が備えられていること、洗った手の再汚染を防ぐように蛇口の開閉が、手を使わずに出来る構造になっていることなどの規定がある。 (e) 工場、設備の設置の仕方、設備・装置は、清浄化が容易な構造であること、冷蔵、冷凍装置の正確な温度の測定装置が必要であること、その他、温度、pH、酸度、水分活性の調節、測定が適切に出来ること、汚染物質が食品に入らないようになっていることなどが規定されている。 (f) 製造やプロセスのコントロール:適切な品質管理が行われなければならないこと、その責任者が決められていること、原料の成分が清潔であり、食品に適したものであることを確認すべきであること、食品およびその加工に使用する水が飲用に適したものであること、容器・運搬車が交差汚染を起こさないように清潔であること、などが規定されており、この義務の遵守はサプライヤー保証などで検証すべきこと。 (g) アフラトキシン、あるいは天然毒素に汚染されやすい原料については、基準値を守ることなどの規定も設けられている。装置は必要に応じて分解して清浄化、衛生化を行うことも規定されている。製造工程については、物理的、化学的、生物的な汚染が起きないように取り扱うこと、そのために守るべきことが、いろいろな工程について、概略、示されている。さらに、汚染が基準値を超えている食品、あるいは原料を、基準値以下のものと混ぜることは禁止されている。こうして基準値以下のものを作っても、それは偽和製品 (食用に適しないもの)とされる。 ■2006年7月18日 HACCPの概要 III. HACCPの発展 最初のHACCPには3原則しかなかった。その3原則とは、(1)製品とそのプロセスに関する安全性問題を明確にする。(2)これらの問題が起きないように、コントロールが必要な特定要素を明確にする。(3)これらの要素が正しくコントロールされていることを確認し、記録するシステムを確立する、の3つである。これらを現在のHACCPにあてはめてみると、(1)ハザード・アナリシス(危害要因分析)、(2)クリティカル・コントロール・ポイント(必須管理点;CCP)の決定、(3)モニタリング手順の確立、ということになる。 HACCPが最初に適用されたのは、その当初の目的のとおり、宇宙食の製造についてであったが(1972年)、1973年には、FDA(食品医薬品局)が、低酸性缶詰食品の製造について、規制を制定した。この規制は、連邦政府規制集(CFR)タイトル21、パート113にあり、HACCPという言葉は使われていないものの、明らかにHACCPの考え方を採用していて、低酸性(pHが4.6以上の製品)缶詰の製造について、必須管理点(CCP)と、その点のコントロールの方法を明らかにしている。しかしながら、その後、食品企業によるHACCPの導入は決して順調に進んだわけではなかった。HACCPの原則の記述は比較的簡単ではあるが、その導入は、それほど容易ではなく、ハザード・アナリシス、必須管理点(CCP)の決定、許容限界(CL)の設定と、それを守ることが出来るようなモニタリング方法の確立には、相当の知識が必要であることが、一部の大企業を除いて、食品企業に容易に受け入れられなかった理由であろう。先発した大企業の一つにマクドナルド社がある。1982年に、ハンバーガーによる大腸菌O157:H7 事件を重大なことと認識した同社は、HACCPを全面的に取り入れることによって、事件の再発を防ぐことにした。その結果は明らかであり、同社に物品を納入する業者にまでHACCPのコンセプトが広がることになった。しかし、これを完全に導入するには、まだ、時間がかかった。 しかしながら、このような、HACCPの導入が遅々として進まないという状況は、1985年に全米科学アカデミーが「すべての規制官庁はHACCPの考え方を採用し、それを食品加工業者に義務付けるべきである」という勧告を発表したことによって、急激に変わることになった。この勧告に基づいて、「食品微生物基準全米諮問委員会(NACMCF)」が1888年3月に政府機関{米国農務省(USDA)、連邦食品医薬品局(FDA)、疾病管理・予防センター(CDC)、商務省の全米海洋漁業サービス(NMFS)および防衛省の獣医局の諮問機関として設立された。この委員会は主に微生物学者からなるものであったが、学術関係者、企業、政府から、アメリカのトップクラスの学識者、実務者を広く集めたものであった。1989年にはNACMCFの中に作られたHACCP作業グループから、最初のHACCP7原則とその食品産業への導入について文書が発表された。 また、1991年に、カナダの食品検査局(CFIA)が「食品安全推進プログラム(FSEP)」を発表し、HACCPは独立してあるものではなく、食品の加工、製造、取り扱いの環境条件を整えることが、HACCPの導入には必要であることが強調された。これが前提条件プログラム(Prerequisite Programs;PP)として、広く受け入れられるようになって行くのであるが、アメリカでは既に、食品製造加工業に関しては「適正製造基準(GMP)」があり、義務化されていたので{CFR(連邦政府規制集)タイトル21、パート110}、これがPPの大きな部分をなすのには抵抗がなかったといえよう。アメリカのHACCPを義務化した規制では、清浄化、衛生化(サニテーション)が特に強調されているが、これはGMPが既に義務化されているので、PPの中でも特に重要なサニテーションの部分を強調したものであって、PPの他の部分が不必要であるということではない。 国連の下部機関であるCodex Alimentarius Commission(コーデックス)もHACCPの概念を安全性の基本として取り入れることになった。HACCPはその後発展し、1997年にはコーデックスおよびNACMCFによって新しい「HACCP原則と、その適用のガイドライン」が発表され、これが現在のHACCPの基本となっている。アメリカでは1997年から数年をかけて、FDA監督下の魚介類および魚介類製品、ジュース類、そしてUSDA(米国農務省)監督下の食肉食鳥肉製品に関して、中小企業を含めてHACCPが義務化された。ヨーロッパでもすべての食品製造に関してHACCPの義務化が発表されている。今後、この傾向は世界的に広まると見てよい。その結果、もし、日本がいつまでも実行不可能な「総合衛生管理製造過程」などにこだわっていると、世界から疎外されていくことになるのではないかという心配がある。中小企業でも実施可能な、世界的に通用するHACCPが広く導入されることが緊急課題である。 ■2006年7月10日 HACCPの概要 II. HACCPの起源 HACCPの発祥は、宇宙開発計画を目指す米国航空宇宙局(NASA)が、1960年代の初めに、食品会社ピルスベリー社に宇宙飛行士の食の高度な安全を保証するようにという要求をしたことに始まったのは、広く知られている。このNASAによる要求は、二つの項目からなっていた:すなわち、(1)食品のくずが散らばって、無重力状態で浮遊し、電気器具などの故障の原因になるのを防ぐこと、(2)病原微生物の混入、増殖、あるいは毒素の存在による食品から発生する危害を防ぐこと、であった。最初の問題は、食品を粘度の高いものにしてチューブに入れたり、食品にコーティングをして一口サイズの物を作ったりして、屑が散らばらないようにすることによって、容易に解決された。しかし、二番目の問題、すなわち微生物的な安全性の確保は、容易に解決できるものではなかった。この時点までの微生物的食品安全性の確保は、製品のサンプリングと検査に依存していたが、サンプリングと検査は、高度な安全性を確保のためには、きわめて効率の悪いものであることが分かった。すなわち、もし、安全性が確保できないような病原微生物汚染が1,000分の1の確率で存在するとする。その10分の1である100個のサンプルを検査した場合、この汚染が発見される確率は約10分の1に過ぎない。したがって、この安全でない製品を、検査に合格させてしまう確率は90%近くあるということになる。現実はもっと厳しく、製品の10%を破壊的検査(製品を消費する検査)することは経済的に到底出来ないことである。 ピルスベリー社のバウマン博士は、「我々は徹底的に評価を行った結果、成功する唯一の道は、全体のプロセス、原料、プロセスを行う環境、それに作業に従事する人々に対するコントロールを確立することであるという結論を出した」と述べている(Kenneth E. Stevenson and Dane T. Bernard, 1995, Establishing Hazard Analysis Critical Control Point Programs, a Workshop Manual, The Food Processors Institute) このような代わりのコントロールの方法は、ピルスベリー社と、米国陸軍の、マサチュセッツ州ネイティックにある研究所との協力で開発された。この方法は、「失敗するモード」と呼ばれる概念に基づいたもので、食品の製品およびプロセスに関する知識と経験の集積によって、何が失敗の原因(ハザード:危害要因)となるであろうか、どのようにして失敗が起きるか、そして、プロセスのどこで失敗が起きるかということを予測して、プロセスがコントロールされているかどうかを明示するような、測定、あるいは観察可能な点を選択し、その点について、コントロールが保たれていることをモニターすることによって、コントロールが外れて、食品安全性の問題が起きる確率が増えるのを防ぐことが可能になる。このようなプロセス上の点をクリティカル・コントロール・ポイント(必須管理点)と呼ぶことにしたのである。このようにして、危害が起きることを防ぎ、製品の安全性を保証できるように、原料、プロセス、製品に関連するすべての因子について、適切なデザインを行うことによって、危害要因のコントロールを行うことを目的とするHACCPが生まれた。 ■2006年7月3日 HACCPの概要 I. HACCP(ハセップ)の概念 非常に基礎的な話から始めたい。「こんなことは知ってるよ」と思われる人も、時には誤解しているところもあるかもしれないので、読んで欲しい。 Hazard Analysis and Critical Control Point(危害要因分析と必須管理点:HACCP)システムは、食品の安全性を確保する、「予防」システムである。これは、農場から食卓までの食品の生産から流通、提供に至るプロセスについて、科学的な考え方と、それに基づいた技術を適用するものである。HACCPシステムは、その実施の容易さ、困難さには差があるものの、農場での食糧生産から、フードサービス(レストラン、ホテル、ケータリング、調理センターなど)、および家庭における食事の調製に至るまでの、あらゆる食品取り扱いのプロセスに適用が可能なものである。 上に、HACCPは「予防」システムであると述べたが、これが、HACCPがその発祥以前の考え方と根本的に異なる点である。すなわち、HACCPの基本は、「検査」より「予防」と言うことであり、食品安全性の危害要因(ハザード)をプロセスの各段階において、除去、減少、混入・増殖防止をすることによって、最終製品に危害要因が、容認できるまで少なくなることを目標とした科学的な手段であるといえる。 HACCPを実施するためには、食糧の生産、加工にたずさわる者、食糧、食品を取り扱う者、流通にたずさわる者、さらに消費者がそれぞれ、自分の取り扱う食物について、安全性問題が起きる過程、それを予防する手段などについて、科学的に裏付けられる知識を持って、それを適用することが必要である。こういうと、何か、深い知識を持って、非常に難しい仕事をしなければならないように思えるかもしれないが、多くの場合、きわめて常識的な仕事をすればよいのであって、どこで、どうやって、という知識さえあれば、予防は比較的容易に達成できるはずである。何を、どこで、については、専門家の知識、科学的なデータが容易に入手できる場合が多い。予防によって、検査が不必要になる場合が多い。 HACCPには、予防を確実に行うために、7つの原則が定められている。これらを段階的に実施することによって、何を、どこで、どうやって、予防するかが明らかにされ、同時にそれを確認(検証)し、記録することが出来る。この原則については、後に詳しく述べるが、ここでは、食物チェーンのすべてにおいて、発生し、混入し、増殖し、残存する危害要因とそのコントロールを明らかにすることが予防に繋がると述べるに止めておく。このような危害要因は、食物に自然に起こる場合もあり、環境に由来する場合もあり、さらに食料の取り扱い中に交差接触(汚染されたものとの接触)や、人為的な過失によって起きる場合もあるが、それをすべてにわたって考慮する必要がある。危害要因の中には、金属破片や、ガラス片のようにその食物を食べる人に怪我や傷害を起こす恐れのある、物理的危害要因、毒性や発がん性がある化学的危害要因もあるが、公衆衛生に観点から、最も頻繁に起き、最も広範囲に起きる恐れがあり、その頻度および重大さが最大なのは、病原微生物などの生物的危害要因である。化学的危害要因は、人々が最も恐れるものであるが、それが、食品中に起きる頻度は比較的少なく、一般的にいえば、その危害の重大さも小さい場合がほとんどであろう。ただし、広範囲に影響する恐れもある。サプリメントについては、危害要因の同定もあまり行われていない様でもあり、コントロールも十分であるとはいえない。現に、いろいろなサプリメントが事故を起こしたという報道もされている。物理的危害要因は、消費者の目に最も見分けやすいものであるため、消費者による苦情の原因になるが、例えば、金属片によって傷害を受ける消費者の数は、一人、あるいは数人に過ぎない。これに比べて、生物的危害要因は多くの人々に危害を及ぼす場合があり、その程度は、一過性の軽い下痢や腹痛で済む場合から、多数の死者を出すに至る場合まである。1985年に米国シカゴの乳業会社で起きたサルモネラによる感染症患者は16,000人あまりに上った。 ■2006年6月26日 法整備の遅れとアカウンタビリティ 一寸古い話になるが、アスベスト被害の拡大、耐震強度の欺瞞、広島の学童殺人、不愉快な事件、悲しい事件が多すぎる。アスベストの事件は議会と官僚の怠慢が真の原因であろうが、アカウンタビリティ(任務遂行責任)の欠如に対する罰則がないことも、これに発する各種問題の頻発を招いている。アスベストの害は、30年以上前に明白になっていたはずである。この時点で、アスベスト除去の法規制を作成、実施しなかった担当官僚は、殺人罪に問われるべきであって、担当大臣や官僚に罰則がまったくないのは、おかしい。耐震強度の欺瞞についても同様であろう。建築設計者、審査者、取り締まり側、すべてにおいて、目の前の不当な利益の追求と、それを許しているアカウンタビリティの欠如ならびにそれを処罰する法規制がないことは大きな問題である。例えば、姉歯設計士、ヒューバー、イーホームなどの責任者は、完全な弁済ができなければ、懲役刑に処せられるべきである。弁済の不足額によって、姉歯氏や、彼に計算をやらせたヒューバーの社長などは30年ぐらいの実刑を受けるようになっていなければ、このような犯罪は後を絶たないであろう。ヒューバーの社長の答弁の一部をテレビで見たが、ヤクザのやり方が見え見えで、非常に不愉快であった。これも実刑30年の口であろう。もし、監査法人がこのような事件を知らずに見逃していたとすれば、監査法人としては全くの失格者であり、ライセンスは直ちに剥奪し、弁済の負担をさせるべきである。このような法整備がきちっとできていない状態で、民間に権限を移行することを決めた政治家も同罪であり、彼らにも議員資格の剥奪、罰金刑および実刑が適用されるべきであろう。広島の学童殺しにしても、アメリカのように、性犯罪を犯したものについては実名と住所を公表していれば、不法入国、再犯は起きなかったのではないか。犯罪者が社会犯罪を犯したと同時に、彼らの市民としての権利が一部制限されて、一般市民がそれ以上の被害を蒙らないようにすることが必要である。加害者にも被害者や一般国民と同等な「市民としての権利」があると考えるのは無責任である。市民としての責任についてもアカウンタビリティが必要である。さらに不可解なのは、「立ち入り強制捜査を年内にやる」という点である。年内にやるからそれまでに記録や証拠書類を隠蔽する時間があると言っているようである。なぜ、疑いがあることが分かった時点で直ちに強制捜査に踏み切らないのか?隠蔽工作を促進している姿勢が丸見えである。これも天下りを始めとする馴れ合いの一環かとさえ、勘繰りたくなる。 そもそも、アカウンタビリティとは何か?「説明責任」は、アカウンタビリティのごく一部に過ぎない。「任務遂行責任」というのが、正しい訳であろう。英英辞典には、accountableとは、responsible for your decisions or actions and expected to explain them when you are askedとなっていて、決定や行為に責任を持つことである。アスベストの問題をなぜ、今まで放っておいたのか、その責任の所在はどこにあるのか、明らかにし、責任を果たさなかった者を罰すると共に、責任を果たさなかった理由を明らかにすべきであろう。私は、アスベストの除去の実施を見送る決定をした官僚、およびそのような決定を推進した議員は殺人罪に相当すると考えている。 実効の上がらない「総合衛生管理製造過程」に固執している厚生労働省の係官も、アカウンタビリティの欠如で訴追されるべきであろうと考える。実効が上がらないことは、この規制を出したすぐ後で、既に明らかになった筈であるにもかかわらず、このようなミステークをなんらの手当てもせずに放っておいたのは、明らかなアカウンタビリティの欠如である。中小企業にまで実施可能な食品安全性確保の手法を直ちに規則化することが必要である。 ■2006年6月19日 ISOとHACCP 規格好きの日本人が飛びつくだろうと思われたISOのプログラムが発表されてから数ヶ月になる。ISO22000がそれである。規格の常として、相当に書類を作る必要があり、今までのISOの例で行くと、実際と書類の整合性が取れそうも無い場合も出て来そうである。中でも「オペレーションPRP」というものがあってPRP(以前のPPと同じ)、PPの中でも特に安全性に重要なものを、厳しくコントロールしようということになっている。オペレーションPRPに属するものは、ハザードアナリシスによって、重大なハザードをコントロールする必要があると認められたものである。これをどこまで広げるかについては、ISO22000では特に指定はないようである。前提条件プログラムとしてこのブログシリーズに書いたものの中から、どれがオペレーションPRPにあたるのであろうか?RTE食品の食品接触面のクリーニング・サニテーションについては、誰もが問題なく非常に重要であるというだろう。しかし、オペレーションPRPをどこまで広げるかについては、「総合衛生管理製造過程」になじんだ人たちが物事を複雑にしかねない。複雑になれば、また、「日本流HACCP」、「完璧主義」、「書面の上のみのHACCP」が出来上がらないだろうか?心配である。ハザードアナリシスでは、Reasonably likely to occurのハザードのみを選び出して、HACCP、あるいはPPで取り扱うことになっている。「Reasonably likely to occur」とは、常識的に考えて、起き易いということであって、重箱の隅を楊枝で掘り返して、あら探しをするということではない。日本でHACCPが普及しなかったのは、完ぺき主義、机上の空論が邪魔をしたので、ある程度ゆったりした考え方をしないと、何も出来ないことになる。その点で、リスクベースのコントロール、コスト・ベネフィット・アナリシスに基づくコントロールを徹底しないと、複雑になるばかりで、コストばかりがかさみ、実務が出来ない。アメリカの魚介類、食肉食鳥肉類の規制で極小企業に至るまで義務化が出来て、成果が上がるようになったのは、この「Reasonably likely to occur」の考え方があったからに他ならない。 何れにせよ、ISO22000のような認証プログラムに人気が集まるのは変な傾向である。HACCPとは、実施するものであって、認証を受けるべきものではない。認証を得たところで、この実施に不備があれば、その場合の食品安全性の確保は出来ていないことになる。なるべく単純明快なHACCP計画を建て、それを毎日、きちんと実施していくのが、食品安全性を確保する道である。 ■2006年6月12日 リスクベースの安全対策(その五) (5)BSE: BSE(ウシ海綿状脳症)およびそのヒトにおける発現の結果である変種クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)は、発症結果が無惨で、治癒の可能性も見られないことから、恐怖を呼び起こす伝達性疾病である。プリオンと呼ばれるたんぱく質のみで構成された伝達因子に異常が生じ、これが通常生体内に存在する正常なプリオンを異常化して疾病を起こすようである。プリオン病としては、ヒツジのスクレイピーがあり、狂牛病として有名になったBSEもヒツジのスクレイピーに原因を発しているといわれる。このBSEが種の壁を越えて、ヒトにも伝達することが分かり、大騒ぎになったものである。 さて、日本でBSE牛が最初に検出されたのは2001年9月であったが、直ちに全頭検査が実施されるようになった。その後も、全頭検査は日本の安全対策が万全であるという証明のように謳われていて、全頭検査を含まない安全対策は不完全であるという考え方が、日本国民に広く行きわたっているようである。しかし、本当に全頭検査は必要なのだろうか?この神話について検討を加える。まず、ヒトがvCJDに罹る確率の問題である。イギリスで発生したBSE牛の数は、確定18万頭、実数は多分100万頭であるといわれる。発生したvCJD患者の数は約150人であるので、6450頭のBSE牛に対して1人の確率になる。これは特定危険部位を食べていたときに罹患した人たちを含む。イギリス人は脳を食べたり、脊髄の入った骨をスープに使ったりしていたので、危険部位を常食していたと言える。特定危険部位を除去すれば、この罹患の確率は約100分の1になる。そうすると、645,000頭のBSE牛に対して1人のvCJD患者が出る確率になる。30ヶ月以内の若い牛のみを食べることにすれば、この確率は更に大きく減少する。(1000分の1以下?)若い牛のみを食べるとすれば、645,000,000のBSE牛の発生に対して1人の患者が出るかどうかという確率になる。日本で25頭のBSEが発生したとすると、30ヶ月以内の若い牛のみを食用に供するならば、25/645,000,000=0.0000000387人のvCJD患者が発生することになるだろう。今まで全頭検査をやった費用をいくらと見るか、議論はあるだろうが、検査そのものの費用だけでなく、人件費、設備費などを含めると1000億円になるという話を聞いたが、そうすると2500000兆円、すなわち250京円を使って、vCJD患者1人の発生を防止できたという計算になる。1000億円の費用の1/10はベースデータを取るのに必要であったとしても、200京円以上の費用が、1人の命を救うのに掛かる計算になる。ヒトの命の大切さには議論の余地がないとしても、これだけの無駄遣いをする資金はどこにもないはずで、他に優先順位が遥かに高い、対費用効果の良い食品安全対策を講ずる必要のあるものが多数存在することは誤りの無いところであろう。 国民の不安を取り除くのであれば、政府はリスクアセスメントを行い、リスクコミュニケーションを行って、透明性を高めることが必要なのであって、金の無駄遣いがこのような形で行われることは、避けなければならない。安全対策の優先順位を確立することは、非常に重要である。科学的な根拠にたって、政策を決めず、行き当たりばったりの仕事をしていれば、国民の不安は益々大きくなり、限られた資金の浪費が止まらないことになる。このような科学的政策の確立は疫学の発達無しには不可能である。リスクベースの分析によって、必要な安全対策の順位を決め、長期計画を立てる必要がある。 ■2006年6月5日 リスクベースの安全対策(その四) (4)食中毒疫学: 疫学には二つの要素がある。一つは、疾病発生の状況の把握である。どのような疾病が、どれだけ出ていて、今後、どのように展開していくのかを調べることがその中心の作業になる。しかし、報告された疾病の統計をとったところで、疾病発生状況が捉えられたということは出来ない。これはCDC(Centers for Disease Control and Prevention;疾病管理予防センター:ジョージア州アトランタにある、アメリカの国の機関で、アメリカ政府のDepartment of Health and Human Servicesに属している)が1996年に発表した「食中毒実数推定値」によって明らかである。報告による統計では、アメリカの食中毒発生数は約6万から7万人であったが、○患者のすべてが医者に行くのではない、○医者がすぐに検便など、原因追及の手段を講じるのではない、○サンプルを採取して、検査にまわしても、病原因子が同定されるとは限らない、○病原因子が同定されても、それが必ず国の機関(CDCなど)に報告されるとは限らない、などのファクターを考えると、報告数の数百倍から一千倍の患者が出ている可能性があるということである。1996年に始まった、代表地域を決めて、それらの地域内で疾病発生状況の積極的調査を行うプログラム、FoodNetは、その後発達して現在では全米10箇所、全米人口の約16%について、積極調査を行って、疾病の発生状況を調べている。この結果、積極的調査を行うことで、実際の疾病発生数の約35分の1が把握されているという状況が生まれている(疾病の種類によって、把握の率は異なる)。FoodNetプログラムの実施の結果、アメリカの食中毒件数の推定は、相当程度の信頼が置けるようになった。日本では、このような積極的調査は大きな規模では行われていないので、報告に頼った統計が用いられているが、上記のように、報告数は信頼できない。 もう一つの疫学の要素は、疾病発生原因の迅速把握である。これは病原因子の同定を意味しているのではない。食中毒発生施設、あるいは食中毒原因食を速やかに同定することである。日本はこの分野でも、世界に大きな遅れをとっている。簡単に言えば、食中毒原因食の同定には、疾病に掛かった人たち(ケース)が何を食べたかを調べるだけでなく、疾病にかからなかった人たち(コントロール)が何を食べたかを調べることによって、どの食物が原因であるかを確率によって決定するという方法(決まった一定のグループについて調べる場合をコホート・スタディと言い、非特定の疾病に掛からなかった人たちをコントロールとする調査を、ケース・コントロール・スタディと言うが、場合によって、使い分けられる)が世界では広く用いられており、過去30年あまりに亙って効果を挙げている。日本ではこれが未発達である。最近になって、漸く、このような疫学手法を理解、解説できる人々が増えてきたが、まだまだ未発達であると言わざるを得ない。 疫学には上記のような要素があるが、疫学の目標は一つ、「疾病の蔓延を防止すること」に尽きる。堺市の大腸菌O157:H7による食物由来の疾病の大量発生を日本で観察した外国の疫学専門家が私に、「日本には疫学が存在しない」と言ったことがあり、(元日本人として)恥ずかしい思いをしたことがある。疫学については、「市民のための疫学入門」(津田敏秀著、緑風出版)および、「食中毒原因食を同定するための方法」(原著IAFP出版、田中信正翻訳、鶏卵肉情報センター出版)などがある。 ■2006年5月29日 リスクベースの安全対策(その三) (3)リスクアナリシス: リスクの評価、その減少への作業には多くのコンポーネントがある。食物由来の疾病について、説明しよう。(a) リスクとは、危害要因(例えば病原性細菌)の量、存在する頻度、その危害要因のもたらす疾病(危害)の重大さ(症状の厳しさ)、病原菌の増減、ドーズ・リスポンス(危害要因の摂取量と、疾病の重篤度の関係)などによって決まる、危害の起きやすさの指標である。この起きやすさを定量的に評価するのがリスクアセスメントと言われる作業である。リスクを減らすように行う作業をリスク・マネージメントというが、これは主に、保健所、厚生労働省などの官庁の仕事である場合が多い。リスク・マネージメントの成功は、リスク・コミュニケーションによるところが大きい。どんなリスクがあるのか、それをどうやってコントロールできるのか、コントロールするためには何が必要か(資金、材料、労力など)を国民に明確にすること、すなわち透明度を保つことが、リスク・マネージメントには必須であり、リスク・コミュニケーションとリスク・マネージメントは一体となって効果をあらわす。この3つのもの、すなわち、アセスメント、マネージメント、コミュニケーションを合わせてリスク・アナリシスという。正確なリスクアセスメントは、リスクアナリシスの基礎であるが、正確さを得るためには、積極的な疫学調査が必要である。 ■2006年5月25日 手術後 5月18日に股関節置換の手術を受けた。関節炎で痛んでいた右股関節の骨盤を削り、大腿骨骨頭を削除し、大腿骨の方は、金属(チタン)で作ったスパイクに丸い頭がついたものを埋め込み、骨盤の方は、金属製のカップに特殊プラスティックのライニングを備えたものを埋め込んで、人工関節を作るものである。手術前の検査は、問診、心臓検査(EKGとEchocardiogram)、X線、血液検査を含むもので、その他に、外科医と、私の家内、私の3者会談があり、そこで、手術、術後のリハビリ、家内への負担に関する説明などを一時間以上にわたって説明し、あらゆる質問に答えてくれるという、徹底したカウンセリングがあった。 手術の2時間前に入院、血圧、体温、聴診など、通常の検査を行った後、手術室に運ばれ、全身麻酔の下に手術が行われた。目が覚めたのは回復室で、痛みと寒気があり、それを訴えたので、直ちに暖めた綿の上掛けが数枚、それに痛み止めのモルヒネがIV(点滴)で供給されたが、そのわずか1時間後には、看護婦の指導で、足の運動を行った。運動は、血栓が出来るのを防ぐことに主眼があるが、痛みにかかわらず、ある程度の運動が強く示唆される。この夜の栄養はIVで取り、傷口には血液などの排出を行うための管が繋がれて、痛み止めは希望によって供給された。手術の次の日の午前中には、リハビリ専門の看護婦が来て、ベッドから起き上がり、ウォーカーを使って廊下に出て、20メートルぐらい歩かされた。午後にもやはり同様に、今度は50メートルあまりを歩いた。このような積極的なリハビリは、「一日寝たままにしていると、回復が3日遅れる」という事実に基づいて行われるのだそうだ。手術後二日目には、クラッチ(金属製の松葉杖のような道具)を使って、廊下50メートルのほかに、階段15段ほどの上り下りをやった。午後にも同様な運動をやり、また、トラピーズ(空中ブランコ)と呼ばれる装置がベッドに取り付けられ、これを使った上半身の運動および下半身のひねりを加えた運動、それに深呼吸を助ける装置を使った呼吸運動を1~2時間ごとに10回繰り返すこと、足に履かされた自動収縮ソックスを用いた強制循環、自発的に行う足首と踵を自分に向かって引き付ける足の運動などが処方された。驚いたことに、初めは痛みなどで大変であった運動が手術後二日目には何とかできるようになり、21日の日曜日には、リハビリの看護婦と医者との両方から退院許可が出て、家内の運転で自宅に戻って来た。 どの程度、家内に面倒をかけるのか、全く分からず、多少の不安はあったが、帰って見て、一夜明けた次の日にはベッドへの寝起きが自力で出来るようになり、トイレも自分で問題なく行け、この面での負担は、あまりかけないで済むことが分かった。ただし、家内には一日3食の負担はあり、手術の際に失った血液(500ml余りだったと思うが)のために体力が落ちているし、心配もかけているので、今後、ますます頭が上がらなくなるのは確かであるが。 退院したとは言っても、放り出されたわけではなく、リハビリ専門の看護婦が週二回、家庭訪問をしてくれ、リハビリの指導と、相談に乗ってくれる。幸い、今のところ、回復は順調で、看護婦を驚かせる結果ではあるが、やはり夕方には疲労もし、患部の痛みもあって夕食後は早めに痛み止めを飲んで寝てしまうという日程にはなるし、まだ、仕事をやろうという意欲は出ない状況ではあるが、今日で手術後8日目、これが大手術を受けて10日経っていない状況かと思うと多少の驚きを感じている。もし、このまま問題が発生しなければ、あと2週間足らずの検査後には、ドライブも出来るし、そろそろゴルフもやれるのではないかと思っている。ただし、手術のショックもあり、日本での不摂生もあって、血糖値が高くなっているのは気になるところである。この辺のことも、アメリカの医者は非常に積極的に関与して、電話での指導、自己管理の指導など、よく連絡してくれ、方向性がつけやすい。リハビリも、このような指導も、すべて予防医学の発達があるためであろう。さらに、3日で退院というのと、3週間入院というのは、経済効果を考えただけでも雲泥の差がある。日本の健康保険は物凄い無駄をしているように思える。 ■2006年5月22日 リスクベースの安全対策(その二) (2) FSO: FSOとはFood Safety Objectivesのアクロニムで、この5、6年の間に世界的に広がってきたコンセプトである。現状で、食品の汚染度がX個/gramであったとする。この際の食物由来の疾病の患者数がYであったとしよう。この患者数をどれだけ減少できるか、その減少のための資金がA円であるとしよう。どんなに頑張ってもA円では患者数は1/2Yにまでしか減らない。しかし、社会的ニーズ(この疾病による経済的損失が現時点ではB円、国民の不安を減らすメリットがC円など)を金に換算すると、疾病を1/4に減少できれば3/4 x B円、国民の不安が仮に半分に減るとすると1/2 x C円の余分な資金が生まれるので、疾病を1/4に減らすために利用できる資金はA円 + B x 3/4 + C x 1/2 = D円となり、これだけの資金が使えることになる。したがって、患者の数を1/4 に減らすことは可能であろう。しかし、これ以上、減らすためには、更に資金が必要であるが、その資金の出所が無い。そうすると、論理的に患者を減らす限度は3/4である。このためには食品の汚染度をX/10にまで減らす必要があり、これはD円の資金で可能であると考えられるし、国民の納得も得られるであろう。この場合、FSOはY/10個/gramとなる。決してゼロにはなり得ないし、ゼロにしようとすれば、とてつもない金が掛かる。このようにして決めたFSOの達成を狙うのが経済的、社会的に正当であると考えられる。やみくもに、達成できない数値をターゲットにするのは得策ではないし、失敗した場合のリパーカッション(反動)が怖い。ただし、このようにFSOを決めるためには、この病原菌と疾病の関係、すなわちこの病原菌についてのリスクアナリシスが完璧に近く出来ていないと難しい。このためには次に述べる疫学がきわめて重要である。 ■2006年5月15日 リスクベースの安全対策(その一) (1) 概論: 食品の安全性に関して、ゼロリスクはあり得ないことを、一般市民が認識することが、安全対策の第一歩である。使える資金の量に限りがあるのは当然なので、この資金を有効に使うことが社会に課せられた義務である。これを無視して、感情にとらわれた、その場限りの対策を、系統立てることもせずにばらばらに、次から次へと適用したのでは、実のある仕事は出来ない。リスクの大きさに基づいて、優先順位を決めて、それにしたがって長期計画を立てない限り、限られた資金、限られた人材が無駄になるばかりである。日本の食品安全性確保の対策は、感情と、思い違いとに支配された、場当たり主義に支配されているように思える。リスクの大きさを正確に評価し、コスト・ベネフィットの効率が最もあがる施策を、優先順位を立てて、長期計画を設置して行かないのでは、先行きが思いやられる。いつも、問題が起きてからの後追いで、国民感情に振り回されているようでは、いつまで経っても進歩が無いだろう。このようなことを、国民に対して十分に説明し、国民を納得させるだけでなく、啓発して行こうという姿勢を持った政治家、官僚、および学者と称する人々があまりにも少ないのではないだろうか。 ■2006年5月9日 アスベスト 姉歯建築士の耐震強度偽装事件は、漸く大きな広がりを見せてきた。あれだけの広範囲の偽装を姉葉だけでできるわけはないので、当然のことであるが、それにしても遅すぎる展開である。政府のコントロールの責任問題にまで発展しなければ、真の解決にはならないが、これは多分、うやむやになるだろう。 このような問題の根源になる、官僚のノン・アクションやイニシアティブの欠如の問題の一つに、アスベストの取り締まりがある。アスベストの害が今更のように大きな話題になっている。欧米ではアスベスト問題を解決すべく、30年以上も前に大きな経費を掛けて、アスベスト除去が行われた。大学の実験室に居た人たちは、アスベストの断熱手袋が、皮製のものに代えられたことを覚えているかもしれない。私が1965年に始めて渡米したときには、アメリカの実験室でもまだアスベストの手袋が使われていたが、その後数年で、より断熱性は低いが安全な皮製のものに代わった。多分、1970年以前だったと思う。 日本では、今ごろになってから、漸く、アスベストの害が、今更のように話題になり、多数の犠牲者を出しているということがニュースになっている。なぜ、このような対策の遅延が繰り返されるのだろうか?問題が顕在化しない限り、対策がとられないという傾向は何もアスベストだけではない。岡山大学の津田敏秀氏は、これは疫学の欠如であると言っている(日本経済新聞)が、私はそれよりも根深い問題ではないかと思う。日本での疫学の欠如は、外国人の疫学者を含めた識者の間では周知の事実であるが、これも含めて、官僚制度の欠陥が根底にあるように思われる。今のように、3年程度でポジションがくるくると変わる官僚制度は極めて大きな害を及ぼしていると思う。3年間という短い期間であれば、何もしないでも時は過ぎる。むしろ、この間に問題を起こさない方が重要であると感じている官僚は多いであろう。特定の分野に深い知識を持つ専門官が常にその場所にいて、彼らの意見が大きな決定力に結びついているということは極めて重要である。日本では専門官もあまり多くはいないのではないかと思われるし、また、専門官の意見が政策に強く反映されることは少ないのではないかと思われる。専門官の意見を用いないのであれば、なぜ、それを用いないのか、理由を明らかにする必要がある。時期を得た適切な政策の展開を監視するために、強い力を持った、産官学民を包括した委員会が存在することが必要である。例えば、アメリカのFDA(Food and Drug Administration;連邦食品医薬品局)では、食品の安全性確保に、「食品微生物基準全米諮問委員会(NACMCF)および科学委員会を設けている。私の仕事に深い関係のあるNACMCFは、産官学消費者を含む各界の一流の専門家、30名近くで構成され、食の安全性確保に大きな影響を与えている。例えば、HACCPの7原則を最初に作成、発表したのはNACMCFである。また、この委員会が委員個人の利益を超越したものであるようにするために、委員は自己の財政状況を公開することが義務付けられている。そして、討議される問題について、自分にConflict of Interest(利害関係の対立)がある場合には、委員会の討議には加わらない。これが30名近い、多数の委員たちがこの委員会に所属している理由の一つである。また、委員は公募制度になっており、真に一流のサイエンティスト達が選ばれることになる。政府機関(この場合は主にFDA)が、この委員会の考えに従わないのであれば、政府側には確固とした理由がなければならない。討議は原則として公開される。また、市民に委員会の考えを知らせるために、公開会議も開かれる。これはこの委員会のみだけではなく、FDA自体の決定についても同様である。 以上、私は、官僚制度の不備を問題にしたが、これには政治家の質の悪さが大きな影響を与えていることは間違いの無い事実であろう。これについては別の機会に述べたい。 ■2006年4月18日 PP とは? PP と HACCP Prerequisite Programs(PP)は日本語では前提条件プログラムといわれている。HACCPを効果的に実施するために必要なプログラムである。ISO22000ではPRPともいわれている。前提条件というと、HACCPの実施に絶対に必要なものであるという印象が強い。部分的には、これは正しいが、PPをすべて完璧に実施しなければHACCPがまったくできないということはない。 Prerequisite Programsという考え方は、カナダの農業食料省の食品安全推進プログラム(FSEP)で最初に指摘されたものであり、HACCPがそれ単独では十分な効果を挙げることが困難であるという事実に基づいていて、現在では、その必要性が世界で広く認識されている。 HACCPでは、製品特有、プロセス特有のハザード(食品を安全でなくする可能性のある要因:危害要因)を、CCP(必須管理点)でCL(許容限界)内にコントロールするのであるが、製品やプロセスに特有でないハザードのコントロールはむずかしい。端的に言えば、そのようなハザードをコントロールするのがPPの役割である。例えば、工場の床や、壁の清浄化(クリーニング)、衛生化(サニテーション)、アレルゲンのコントロール、従業員の行為から発生するハザードのコントロール、食品接触面の清浄化、衛生化、工場の環境、などは、PPに属する。 ここで注意しなければならないのは、(1)PPの項目は非常に多いこと、(2)中には安全性にも関係はあるだろうが、それ以上に品質に重要な項目もあること、(3)PPを完璧に行うことは困難であること、(4)PPが完璧に行われないからといって、食品安全性に対するハザードが直ちに増えるとは限らないこと、(5)PPの不完全さはリアルタイムでモニターすることが難しいことなどであり、この点で、PPの管理点におけるコントロールは、リアルタイムのモニタリングが、コントロールの鍵になる、HACCPのCCPのコントロールとは性質が異なるのである。 アメリカFDAの魚介類のHACCP規制において、サニテーションの重要性が強調されているが、これは、PPがサニテーションのみで出来ているということではない。FDAの食品の安全性に関する規則は、GMP(Good Manufacturing Programs;適正製造基準)が既に確立されていて(連邦規制集タイトル21、パート110)、それが前提になっているために、特にサニテーションに焦点を当てることが可能なのである。この辺の実施状況や法規制が不十分な日本では、PPの中に、サニテーションのみでなく、その他の項目が当然入ってくる。ここにいう、その他の項目の中には、(1)アレルゲンのコントロール、(2)リコールおよびトレーサビリティ・プログラム、(3)サプライヤー品質保証プログラム(Supplier Quality Assurance Program)、(4)環境モニタリングプログラム、(5)工場およびその設備などの温度コントロール、(6)工場施設および設備の衛生的デザインなどが含まれるであろう。 これらの多数のポイントをすべて完璧にコントロールすることは不可能であるばかりでなく、不必要であるといっても差し支えない。完璧性とは、HACCPのCCPのように、許容限界(クリティカル・リミット)を定め、リアルタイムでモニターし、許容限界を逸脱している場合には、是正措置をとるということであり、これをPPの多数のポイントにも当てはめようとすると、プログラム全体が極めて複雑なものになって、実施不可能になる。このような誤解に基づく実行不可能なことを強いているのが、日本の総合衛生管理製造過程であるといっても過言ではないだろう。これが日本でHACCPが普及しない大きな原因でもあるだろう。 PPをどこまで行う必要があるかは、ハザードアナリシス(危害要因分析)によって決める。PPを可能な範囲で行って、その結果、HACCPでコントロールしにくいハザードが、どれだけ減少したか、どこまでコントロールできているかを分析し、その結果、PPの改善の必要性を評価し、是正すべきは是正して、HACCPへと進むのである。決して完璧さを求めてはならない。なぜならば、PPの完璧さを求めれば、既に述べたように、プログラムが複雑になるだけで、効果が上がらないからである。ゼロ・リスクを求めるのは決して得策ではない。むしろ有害でさえあるということを認識すべきである。 日本の食品安全性に関する法規制では、このようなメリハリが不在であるため、何をどれだけコントロールするのかが明確にならず、いたずらに完璧性を求めて失敗している。まずGMP、サニテーションプログラムを数年掛けて実施したうえで、HACCPを導入すべきである。あせって、すべてを同時に行おうとすることは得策ではない。 ■2006年3月6日 「誰にでも出来るHACCP」と「誰にも出来ないHACCP」 アメリカでは魚介類製品、食肉食鳥肉製品およびジュースの製造において、HACCPが、中小企業も含めた全ての企業に対して義務化されている。このためにはHACCPは「誰にでも出来るHACCP」でなければならない。このようなHACCPは、NACMCF(食品微生物基準全米諮問委員会;HACCPの7原則を最初に確立した、アメリカ政府に対する諮問機関)のガイドラインにほぼ、忠実に添っている。 日本ではどうだろうか?厚生労働省の、特定の製品に対する「総合衛生管理製造過程」は、前提条件プログラム(PP)とHACCPの区別ができていないこと、PPの数多いコントロール・ポイントを完璧にコントロールしようという、実現不可能な目標を立てていることから、実施不可能なプログラムになっている。したがって「総合衛生管理製造過程」は認証を受ける時点では紙の上では全てが出来ているように見えるとしても、これを毎日実施することは、その複雑さゆえに、不可能である。PPのコントロールと、HACCPのコントロール(CCPによる)とは異なるというのは、世界中で認められたことである。なぜ日本だけが違うことをやろうとするのか、違うことが出来ると考えるのか、私には全く理解が出来ない。「日本はユニークである」と考えている人たちが多いようであるが、そう考えることがユニークである。日本だけ特別であると思うのは、井の中の蛙であるか、または思い上がりではなかろうか。もっと大幅に国際性を高めないと、全てにおいて、努力をする割には成果が上がらず、国際性がますます薄れてくる。「誰にも出来ないHACCP」を捨てて、「誰にでも出来るHACCP」を導入すべき時期が来ている。今まで実効の上がっていない「総合衛生管理製造過程」を廃止して、実効の上がるシステムを実施することが必要である。「官僚は過ちを犯さない」と言った官僚がいるそうだが、思い上がりもはなはだしい。官僚のやることは過ちだらけであるが、それは大きな問題ではない。過ちを早急に修正して、正しい方向へ舵を取り直すことが重要なのであって、それで面子が潰れると考える方が問題なのである。このように考えることによって、もっといろいろな施策を実施することが出来る。不作為の罪は大きい。このような過ちは官僚のみが犯しているのではない。原文を読まず、理解もせずに、自分の思い込みだけで勝手なことを言っている人々が余りにも多い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||